【PR】
こんにちは、てっつーです。
健康診断で再検になり、心配になってきたこの頃。
そろそろ食事や健康管理しなきゃとと思いながら、なかなか進まない。
そんなお悩みありませんか?
いきなり結論ですが、減塩上手な人たちはみんな「美味しく減塩できる味」を覚える所から入っています。
圧倒的なスピードで減塩生活することができます。
我流で減塩始めるより、何十倍も早いのではないかと思います。
例えば、何か新しいこと始める時は「◯◯教室」に行ったりするのではないでしょうか?
スポーツで言えば、コーチについてもらって正しい指導を受けると、早く成長できますよね。
プロのサッカー選手になる人たちは、家の庭だけでボール蹴ってプロなったわけでは無いですよね。
料理でも同じことが言えます。
初心者の頃って、レシピ通りに作りますよね。
まず基本の味を覚えてからオリジナルを加えていきますよね。
まずは
「美味しい減塩とは?」や「減塩した場合の1食あたりの塩加減」を覚えてから、塩味を減らした料理作りに入ったほうがいいです
美味しくないと続けるの難しいですよね。
で、だんだん減塩の加減を覚えてきてから、自分オリジナルの料理なんかを作るという流れなのではないでしょうか?
最初から我流でやる方が失敗しやすいですよ。
美味しくない ⇒ 続けられない ⇒ 負のループに陥りやすいです。
減塩が続かない理由と「真似」の大切さ

そもそもなぜ減塩生活が続けられないのでしょうか?
それは減塩にした時に
- 美味しくない
- 最初から「薄味=我慢」と思い込んでいる
- 我慢がストレスになる
- 出来なかったときに自己嫌悪になる
色々な原因が考えられます。
多くの失敗の原因は、我流だけに頼る知識の無さが原因です。
決して、「自分が料理下手なんだ~」を凹む必要はありません。
もちろん工夫や挑戦することすばらしいですが、我流だけでは危険です。
👉減塩上手な人の工夫を真似するだけでいい と考え方を変えてみませんか?
真似して美味しく減塩するためのコツ

減塩する際のコツやポイントを確認していきます。
参考にしたのは、全国健康保険協会(協会けんぽ)です。
- 薬味や香辛料を効かせる
- しっかり味付けしたものは1品
そのほかの料理にはできるだけ塩分を使わないようにする - 汁物は具沢山に
- レモンやゆず、酢などを利用して酸味を効かせる
いずれも美味しい食事に共通することですね。
数字で見る減塩の目安と栄養バランス

減塩の目安を確認していきましょう。
全国健康保険協会(協会けんぽ)から塩分の基準をピックアップしました👇
- 1日男性7.5g未満、女性6.5g未満(日本人の食事摂取基準2020年版)
- 血圧の検査で基準値以上
👉「1日6g未満」を目標
日本では塩分摂取量の現状は、平均10.1g(令和元年国民健康・栄養調査)です。
多くの人は基準値を上回っていることになりますね💦
1食あたり塩分2.5g以下を目指す

1日の食塩摂取目標量が成人男性7.5g未満、成人女性6.5g未満とされています。
3食で割ると1食あたり食塩は約2g~2.5g程度が目安となります。
これは思ったよりも少ない量です。
特に自炊をしない方は、商品の裏面を見てチェックしてみましょう。
👉まずは自分が取っている塩分量を確認することが大事です。

加工食品は手軽ですが、塩分量の高さにびっくりします。
野菜・タンパク質・カロリーとのバランス
減塩を意識すると「味が物足りないのでは?」と心配になりますが、実は食材の組み合わせで満足感を得ることができます。
👉特に大切なのが 野菜・タンパク質・カロリー の3つのバランスです。
間単に役割を確認します。
- 野菜:食物繊維やカリウムが豊富。余分な塩分を体の外へ。
- タンパク質:「噛みごたえ」と「旨味」があり、減塩でも美味しく。
- カロリー:低塩分でも揚げ物や脂質が多いと健康に逆効果。
この3つを意識するだけで、「減塩しながら満足感のある食事」に変わります。
実際に真似してみた!私の減塩体験談
最初は「自分で工夫すれば減塩できるはず」と思い、出汁を効かせたり、レモンや酢で味付けしたりと試してみました。
ところが、 家族の味覚に合わせる必要があったり、忙しい日に時間をかけられなかったり して、結局「今日は普通に味噌・醤油を使おう…」と妥協する毎日・・・。
減塩を意識すればするほど、日々のストレスが増えていってしまいました。
減塩レシピを真似してわかったこと

ネットや雑誌に載っている「減塩レシピ」を真似してみると、確かに美味しく仕上がるものも多くありました。
でも、材料を揃えるのが大変、作り慣れていないから味が安定しない といったことがありました。
特に平日は仕事終わりに料理するだけで大変。
結局休日だけの取り組みになってしまい、継続が難しかったです。
宅配食を試して「美味しい×健康」を実感


そんなときに出会ったのが「わんまいる」の美食弁当。
1食ごとに栄養バランスが整っていて、 塩分2.5g未満・カロリー300kcal以下・タンパク質15g以上 と安心できました。
さらに驚いたのは、味が「薄い」どころか 出汁や素材の旨みで満足感があること。
自炊では難しかった「美味しさ」と「健康管理のしやすさ」が、簡単に手に入るのは助かります。
冷凍って美味しくなさそう?と最初思いましたが、むしろ素材の香りが強くてびっくり。
なるべく朝市場で仕入れたものをカットして調理しているそうです。
他の宅配食に比べ、素材の味がしっかりしているなと感じます。
一つデメリットがあるとすると、少し冷凍庫を空けておかなくてはならないことです。
商品到着前から少し冷凍庫を整理しておけば良かったな~と少し焦りました💦

減塩を無理なく続けるための宅配食という選択肢はあり?
👉宅配食はありだと感じました。
理由は2つ
- 塩分管理が簡単
- 適当な塩分量を体で理解できる
結果、普段から塩分取りすぎてたんだ・・・と気が付くことができました。
今までは何も気にせずバクバク食べていたものも、今では控えるように。
普段のご飯を1食置き換えることで、健康管理を学びながら食事できるイメージです。
栄養面も整います。
特に忙しい人には試してみる価値ありのサービスだと思いました。
減塩で「美味しい×健康」わんまいる美食弁当

最後にわんまいるが良かったこと、4選にまとめて振り返ってみます。
✅1食あたり塩分2.5g未満
✅国産食材&出汁の旨味で美味しい
✅続けやすい冷凍保存と調理の手軽さ
✅初回セットで気軽にお試しできた!
👉美食弁当は5食セット初回税込5,780円(送料別)。
※送料がかかります。お住まいの地域はいくらか事前に確認しましょう。
【1回の送料】
北海道・沖縄・離島以外:1,080円(税込)
北海道・沖縄・離島:2,645円(税込)
詳しくは下記から確認できます
よくある質問
わんまいるのよくある質問をまとめました。
ぜひご参考にしてください。
- Q減塩食は味が物足りない?
- A
正直、最初は物足りなさを少し感じました。
しかし、適正な食事から自分の食生活とギャップがあったことが原因です。
徐々に体が正しい食事に慣れていく感覚が楽しくなってきます。
- Q家族と一緒に食べても大丈夫?
- A
はい。
栄養バランスはしっかり確保されています。
大人から子どもまで安心して食べられる内容で、普段の夕食に取り分けても自然に楽しめます。

実際に食べてみて、食材は柔らかく、魚は骨がほぼありませんでした。
取り分けやすかったです。
- Q宅配弁当は高くない?
- A
美食弁当は5食セット初回5,780円(税込・送料別)。
1食あたり約1,156円。
栄養管理や調理の手間を省け、コストパフォーマンスは高めです。
- Q賞味期限はどのくらい?
- A
冷凍保存で約4〜6か月が目安です。
最低でも賞味期限1ケ月あるものが届きます。
- Q解約や一時停止は簡単?
- A
定期コースにしばりはなく、メールや電話で簡単に解約・一時停止が可能です。
マイページからも確認できるので安心です。
- Qご飯はついている?
- A
お弁当はおかずのみです。
ご飯は自宅で炊いたものや雑穀米と組み合わせるのがおすすめです。
- Q宅配ボックスへの配送は可能?
- A
冷凍便のため、基本的に手渡しでのお届けになります。
まとめ

美味しい減塩料理の味を徹底的に覚えたしたからこそ、私は一日の食塩摂取量7.5g位で満足できてます。
つまり、
・自炊の際は美味しい減塩料理をパクリまくったということ。
・実は参考にしたのは今回紹介した宅配食のわんまいるやナッシュです。
パクったおかげで、美味しく続けられています
逆に、もしも僕が「宅配食」のやり方を真似ないで、最初から「気合で頑張る!我慢を続ける!」なんてやってたら、間違いなく続かなかったと思います。
今も、食欲に負け、自分に嫌気がさす毎日だったでしょう。
このように考えると、本当に美味しい減塩料理の味を真似してよかったです。
美味しい減塩料理を知るため・続けるために、これからも僕は食に投資していくことでしょう。
その方が、コスパもいいし健康的ですからね!
関連記事
ここでは減塩や健康管理に役立った宅配食、自分のうまくいった健康管理について記載しています。
ぜひご参考になれば幸いです。

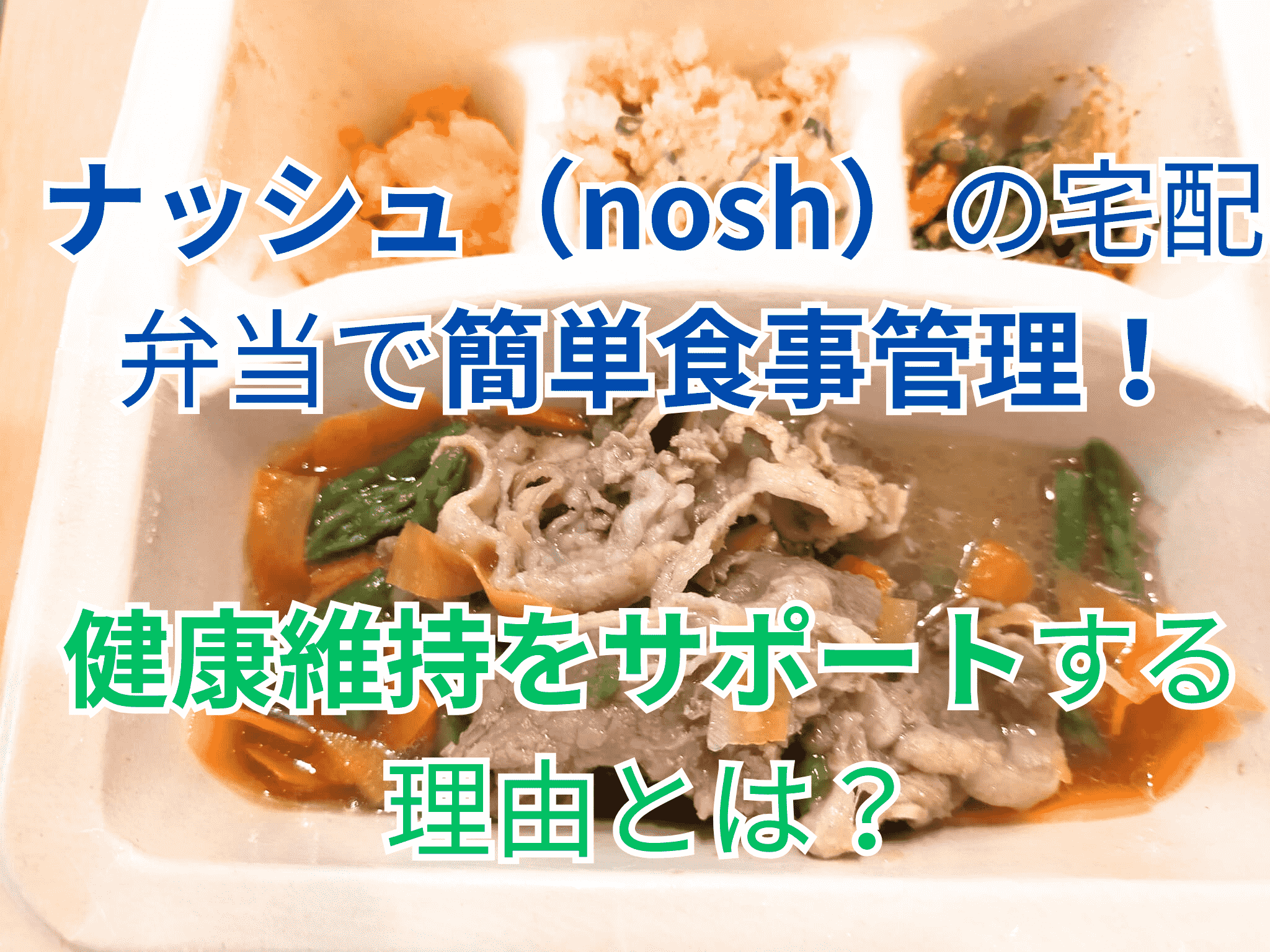

最後までお読みいただきありがとうございます。
皆様の生活がよりよく、楽しいものになれば幸いです。
- こんな方法で食べる時間を楽しくしている
- 健康を意識した食事
- 子育て中の方の工夫
などありましたら、コメントいただけると嬉しいです。
おわり




コメント